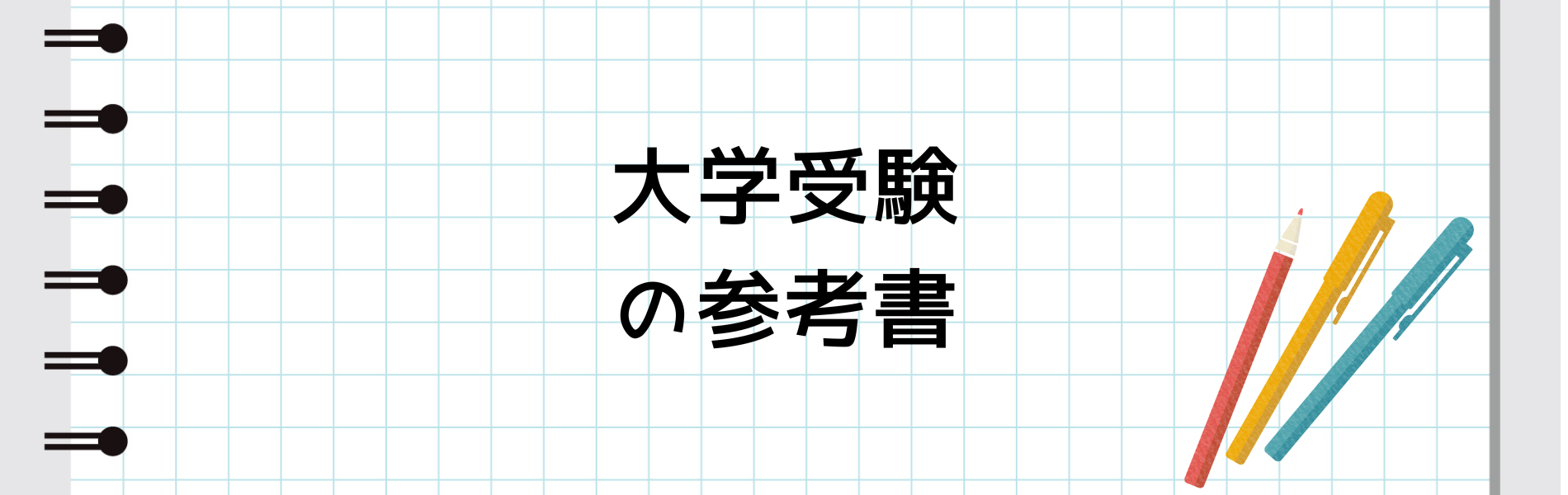※このページはプロモーション(広告)を含みます。

受験勉強をする上で必要なことのひとつとして、「志望校選び」があります。志望校を決めることで目標が定まり、やるべき勉強を絞ることができます。また、「自分がやりたい仕事に関することを学べる大学」や「雰囲気の良い大学」を見つけることで、受験勉強へのモチベーションが高まります。
ただ、「どうやって志望校を選んだらいいのか分からない」ということは多いです。大学受験では「志望校の選び方」があります。まずは選び方を知ることが大切です。
ここでは「大学受験をするにあたり、志望校をどのように選べば良いか」について紹介します。自分に合った志望校を決めて、受験勉強をスタートしましょう。
なお、大学に関する情報をチェックするなら、「マイナビ進学」というサイトはおすすめです。会員登録をすると、大学の資料やパンフレットを取り寄せることができます。会員登録は無料なので、ぜひ活用してください。
志望校は受験勉強を始めるときに決めるべき
志望校は大学受験に向けた勉強を始めるときに、決めておくと良いです。志望校を決めると「ゴール」が決まることになります。つまり「志望校に合格するための学力を身に着けるため」に、勉強をすれば良いのです。
志望校を決めずに目の前の勉強をしていても、学力を上げることはできます。ただ、より効率良く勉強を進めるためには、先に決めた志望校の入試に向けて学ぶほうが無駄がないのです。
「志望校を決められない」「志望校を決めるのは面倒」と思うことがあるかもしれません。ただ、それは単純に「志望校の決め方」を知らないだけの可能性があります。下で紹介するポイントを確認して大学の情報を見ると、興味をもてる大学が見つかるはずです。
まずは第1~3志望を決める
志望校を決めるときには、まずは第1~3志望まで決めると良いです。大学の情報を見ていると、どの大学が1番良いか決められなくなることがあります。この場合には最もレベル(偏差値)が高い大学を第1志望にすると良いです。その学力を身に着けることができれば、ほかの大学の入試にも対応しやすくなるためです。
また、興味のある大学が3つ見つからなくても、第1志望に近いレベルの大学を差し当たって2つ選んでおきましょう。「万が一第1志望の大学に対応できる学力を身に着けることができなくても、ほかにも良い大学はある」と考えられるようになると、受験勉強をするときに心の余裕が出てきます。「すべり止めの大学がある」と思えると、受験のプレッシャーを軽くすることができるのです。
途中で志望校を変更しても問題ない
志望校は途中で変更しても問題ありません。高校には高2や高3の時点で志望校を伝えることになるかもしれません。しかし最終的には、自分で受験する大学を決めることになります。
最終的に大学入試を受ける申込みをするのは、「高3の1月下旬から」です。それまでは志望校を変更することができるため、勉強をする中で、あらためて志望校について考えるのも良いです。
勉強をしていると、「思ったより成績の伸びが良い」という場合があります。このときには第1志望の大学を変更して、「興味はあるけれど今までの学力では目指せなかった」という大学も視野に入れると良いです。
ただ、志望校のレベルを下げるのは、あまりおすすめしません。途中で「自分には難しい」と考えて志望校のレベルを下げてしまうと、モチベーションが下がったり、難易度を下げた大学に学力を届かせることも難しくなってしまったりします。
志望校のレベルを上げたり、候補の数を増やすのは良いですが、レベルを下げるのは入試を申し込む1月直前にしましょう。現役生は高3の冬から急激に成績が伸びるため、最後まで諦めないことが大切です。
ちなみに「どうしても志望校を決められない」という場合は、まずは勉強量が多い「英語」と「数学」の勉強から始めて、これと合わせて志望校についても考えていきましょう。当面は自分の学力で目指せるレベルの大学を志望校に決めておき、あとから変更すると良いでしょう。できれば高3の夏休みまでには、志望校を決めるほうが良いです。
大学を選ぶ9つのポイント
ここからは、大学を選ぶ基準になるポイントについて紹介します。どのような点に気をつけて大学の情報をチェックすれば良いのかを知ることで、志望校を決めやすくなります。
学びたいことが学べる学部・学科があるかどうか
まずは大学に、自分が興味のあることが学べる学部・学科があるかどうかを確認しましょう。大学によって文系と理系、どちらの学問が盛んなのかは異なります。
たとえば「東京大学」は、文系と理系どちらの学生も学ぶことができる学部・学科があります。これに対して「一橋大学」は文系の学問を学びたい人におすすめの大学です。また、私立の「東京理科大学」は、理系の学問を学びたい人専門の大学です。
また、大学の学部・学科選びをするときには、そもそも「自分が何を学びたいか」「将来どんな仕事をしたいのか」について考えておく必要があります。今まで考えたことがなかった場合は、自分の将来について、考えてみることをおすすめします。
たとえば「車が好きで、車に関係する仕事をしたい」ということなら、工学部の機械系や電気系の学科を目指すと良いです。「先生」になりたいなら教育学部、ビジネスについて勉強したいなら経済学部や商学部などが良いです。
最近は大学ごとに学べる学問が細分化されていて、より学生が学びたいことを追求して勉強できるようになっています。いろいろな大学の情報を眺めていると、「これは楽しそう」「面白そう」と思える学部や学科が見つかりやすくなります。まずは気軽な気持ちで大学の情報を見てみることをおすすめします。
難易度(偏差値)
大学の難易度も大切な基準になります。一般的な傾向として、上位レベルの大学は学問を学べる環境が充実しています。世界でも最先端の研究を行っていたり、有名な教授が講義をしてくれたりします。ただし、単純に「レベルが高い大学だから」という理由だけで、大学を選ぶべきではありません。
多くの受験生が「難しい大学のほうが目指しがいがある」と考えて大学を選びがちです。しかし、自分が興味のあることを学ぶことができなければ、偏差値の高い大学を卒業しても意味がありません。仕事を始めるときに、学んだことを活かすことができないためです。
偏差値は大学選びの良い基準になりますが、必ずそれに加えて「将来やりたい仕事」や「なりたい職業」について考えて、それに役立つことを学べる大学を選ぶようにしましょう。
大学の場所
大学の「場所」も大切な要素です。大学に入学すると毎日通うことになるため、大学がどこにあるのかは大切です。
大学生には「実家から大学に通う人(自宅生)」と「大学近くのアパート・マンションに1人暮らしをして、通学する人(下宿生)」がいます。実家から通う場合には大学への交通費だけですみますが、1人暮らしをする場合には、住むアパートやマンションの家賃や、電気・水道・ガス代などがかかります。
志望校を決めるときには、「東京の大学に行って、東京で生活してみたい」「1人暮らしを経験したい」のような考えで大学を選ぶ人がたくさんいます。「自分の興味のあることが勉強できる」ということは大切ですが、憧れの大学生活ができる学校を志望校に決めることも良いと思います。
東京の大学を志望校にしたり、下宿を検討したりする場合には費用がかかるため、家庭内で相談することをおすすめします。
国公立か私立か
大学は大きく分けて、国や県が運営している「国立大学(国が運営する大学)」「公立大学(県が運営する大学)」と、大学自体が独自に運営している「私立大学」があります。国立大学と公立大学は、「国公立大学」とまとめて呼ばれることが多いです。
国公立大学と私立大学の大きな違いに「学費」があります。国公立大学のほうが圧倒的に学費が安く、年間の学費は約50万円です。これに対して私立大学は年間で約100~130万円の学費がかかります。また、国公立大学のほうが偏差値レベルが高い傾向にあります。もちろん私立大学にも難易度が高い大学はありますが、国公立大学のほうが難易度が高い大学が多いです。
研究設備に関しても、国公立大学のほうが国や県という大きな組織が資金を提供しているため、整っていることが多いです。
ただ、大学は学ぶ「環境」や「雰囲気」も大切な要素です。一般的な傾向として、国公立大学は「落ち着いた雰囲気」、私立大学は「明るくお洒落な雰囲気」のイメージがあります。私立大学は国公立大学に負けないよう、大学内のキャンパスをきれいに整えたり、お洒落な学食やカフェなどを設置していることがあります。
このように、国公立大学と私立大学には、どちらもメリットとデメリットがあります。両方を比較して考えるようにしましょう。
大学の雰囲気・伝統・イメージ
大学によって、雰囲気やイメージは異なります。また、大学によっては長い伝統を誇っている学校があり、こうした点を重視して大学を選ぶのもひとつの方法です。
たとえば分かりやすい例として、「東京大学」や「京都大学」は「日本トップレベルの国立大学」というイメージを多くの人がもっています。また、「早稲田大学」や「慶應義塾大学」は、「日本トップレベルの私立大学」「学生が明るい」のようなイメージをもつ人が多いです(もちろん人によって、イメージに多少の差はあるかもしれません)。
自分のイメージに合う大学を選ぶようにすると、同じことを学ぶときにもより楽しく、積極的に学ぶことができるようになります。せっかくの大学生活なので、「充実した毎日を送れそう」と思える学校を選ぶことが大切です。
大学の設備・環境
大学によって設備や環境は異なります。研究設備が整っていたり、学生が自由に使えるスペースが設けられていたりする大学があります。
大学のホームページでどのような設備があるかを確認することができますが、できれば「オープンキャンパス」で実際に大学を見に行ってみると良いです。インターネットで得られる情報は大切ですが、実際に目で見て体験してみることで、初めて分かることもあります。研究設備や大学の施設は、実際に見てみると大規模で驚くことは多いです。
また、設備や環境を良いと思えるかどうかは、やはり自分自身で直接判断するほうが良いです。評判などを聞いても、自分が同じように感じるかどうかは分かりません。
オープンキャンパスに行くと、モチベーションが高まることが多いです。実際に大学の風景を目にすることで、「受験を頑張って、この大学に入ろう」という気持ちを強く持つことができるようになります。
オープンキャンパスはそれぞれの大学が5~9月ごろに無料で開催していることが多いです。志望校を決めたらオープンキャンパスの日程を確認して、実際に足を運んでみることをおすすめします。
オープンキャンパスについては別記事で紹介しているため、こちらも参考にしてほしいと思います。
>参考;「オープンキャンパスのメリットや行くべき理由。服装・持ち物・親同伴」
就職支援が充実しているかどうか
大学生活を終えると、一般的には就職をして、企業で仕事をすることになります。ただ、近年は大学を卒業しても就職できないことが増えてきています。
大学には「就職率」というデータがあります。就職率は、「その大学を卒業した人がどれだけ就職できたか」を示す数字です。就職率が高いほど「その大学に入れば、将来的に企業で仕事をできる可能性が高い」ということがいえます。
大学は就職率を上げるために、「就職支援」を行っているところがあります。特に私立大学は就職支援に力を入れていることが多いです。こうした大学では学校内で企業の説明会が行われたり、大学受験の予備校のように大学のスタッフが「就職のサポート」をしてくれたりします。
就職支援に力を入れている大学は、大学のホームページで特徴として紹介していることが多いです。就職支援の有無を確認して、志望校を選ぶのもひとつの方法です。
学費
大学によって学費が異なります。上でも紹介したように、国公立大学は年間の学費が約50万円、私立大学は年間で約100~130万円ほどの学費が必要です。また、私立大学の医学部はより高額な学費になっている場合があります。
できるだけ学費を安く抑えたい場合は、国公立大学を志望校にすると良いです。大学は4年間、大学院まで進学する場合は6年間などの期間を過ごすことになります。そのため、費用と合わせてほかの面も考慮して選ぶことが大切です。
家庭によって予算は異なるため、親子で相談して決めることが大切です。
部活・サークルが充実しているかどうか
「大学に入学したら、部活やサークルを頑張ろう」と考えることもあると思います。大学によって部活やサークルの種類は異なるため、前もって確認して興味のあるものがあるかどうかを確認しておくと良いです。大学生活は勉強も大切ですが、部活やサークルに打ち込むことも良い経験になります。
全てを100%満たす大学はない
以上のポイントについて考えるようにすると、志望校を決めることができるはずです。ただ、全ての希望を100%満たす大学はほとんどありません。どの大学にも良い点とそうでない点があるため、それぞれのポイントを確認して、総合的に判断することが大切です。
また、志望校は1度決めてもまた変更することができます。頻繁に変えすぎるのは良くありませんが、3ヶ月や半年に1度など、志望校について考える時間を取ると良いです。そうすることで、自分の実力や目的に合った志望校を設定しやすくなります。
大学探しができる4つのサイト
最後に、大学情報の検索をすることができるサイトを4つ紹介します。志望校選びに役立つため、活用することをおすすめします。それぞれ会員登録を無料でできるので、登録してブックマークしておくと便利です。
マイナビ進学

マイナビが運営している進学情報サイト。リクナビ進学と似ていますが、「オープンキャンパス」「進路相談会」「学園祭」など、大学で開催されるイベントでも検索しやすくなっているのがメリットです。また、自分の将来について適性が分かる「適学診断」を無料で利用できます。無料で資料請求もできるため、リクナビ進学と併用することで全国の大学をほぼ網羅できるはずです。
>>「マイナビ進学」
Benesseマナビジョン(ベネッセ)

「進研ゼミ」でおなじみのベネッセが運営している情報サイト。入試情報のほかに大学の概要や初年度納入金、奨学金などについて知ることができます。
大学受験パスナビ

大学受験教材を多数出版している旺文社が運営するサイト。大学の入試情報を詳しく検索することができます。
おわりに
大学受験での志望校は、以上のようにして決めることができます。志望校について考えることは、「将来」について考えることでもあります。とても大切なことなので、これまで考えていなかった場合には時間を取って決めてみましょう。
志望校を決めることができると、受験勉強もやるべきことがはっきりして、取り組みやすくなります。また、「この大学に入りたい!」という大学を決めることができると、モチベーションがとても高まります。
志望校が決まったら、合格に向けて受験勉強をしっかり頑張っていきましょう。