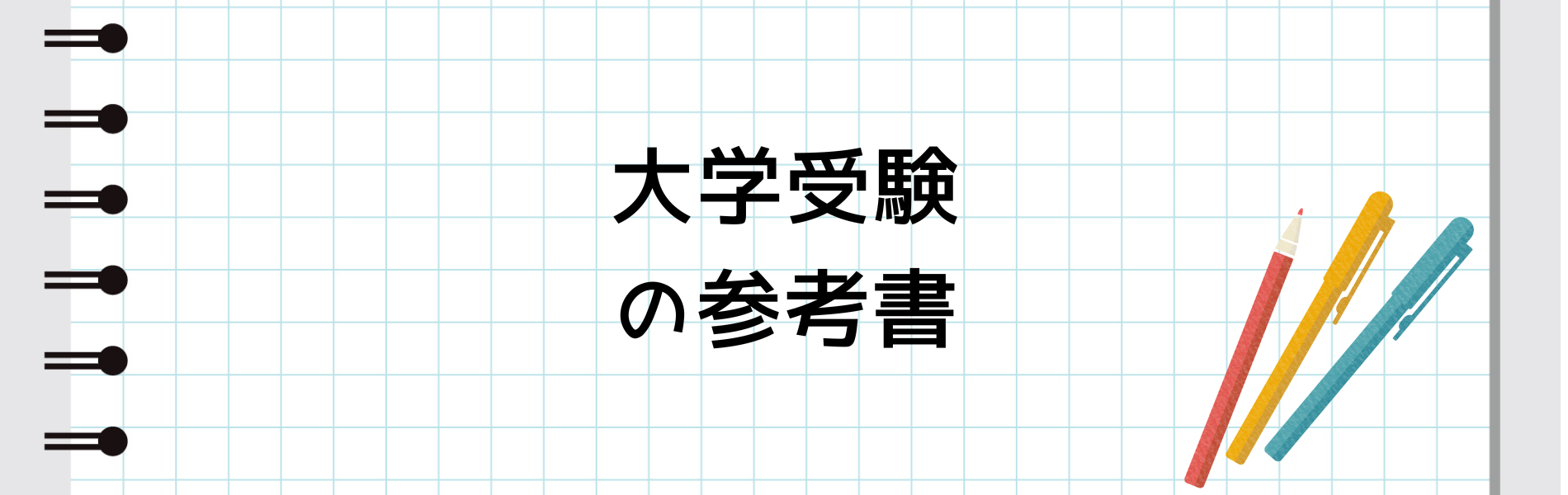※このページはプロモーション(広告)を含みます。

受験勉強を頑張ったとしても上手く成果を出すことができず、やむを得ず浪人をすることもあると思います。浪人生活は高校生でも大学生でもない生活になるため、「どうやって過ごせばいいのだろう」と不安になることがあるかもしれません。
私も浪人を経て大学に入学しましたが、やはり高校生活と違う部分があり、気を付けないといけないこともありました。
ここでは、私の浪人時代の体験談を紹介します。「どのような生活スケジュールだったのか」「どのようなことに気をつけていたのか」などについて紹介しているので、参考にしてほしいと思います。
ちなみに私は「積極的に浪人する必要はないけれど、浪人生活は有意義だった」と思っています。落ち込んでしまうことがあるかもしれません。ただ、取り組みかたに気をつければ、浪人生活を良いものにすることができます。
浪人でも学力は伸びる
最初に、浪人でも学力は伸びます。よく言われることに「現役生のときに精一杯勉強したのだから、浪人しても学力は伸びない」という話があります。しかし、実際に浪人を経験していない人が、こうした話をしていることがあります。
私は浪人した経験がありますが、現役のときには合格できなかった名古屋大学に合格することができました。自分自身の経験から、「浪人をすれば現役のとき以上に学力を伸ばすことができる」と言えます。また、私が仕事をしていた塾でも、浪人をして現役のときには届かなかった大学に合格した人がたくさんいました。
そのため「浪人生は現役以上に伸びない」と言われても、気にせずに頑張りましょう。
私も浪人をするときに周りの人からこのように言われたことがあります。ただ、「結局は自分次第だ」と思っていました。
必要なことを学んで理解して、入試問題を解けるようになれば学力は伸びます。周りの人からの言葉で「どうせ浪人生しても伸びない」と落ち込んでしまうより、やるべき勉強に取り組むことが大切です。
「強い気持ち」をもつことが大切
周りの人からの言葉を気にしないようにしていたとはいえ、浪人するとき、私はやはりプレッシャーを感じていました。「これから1年もう一度勉強して、合格できなかったらどうしよう」「やっぱり現役のときが、自分の限界じゃなかったのか?」のような不安がありました。また、思うように勉強が進まないときや、模試であまり点数を取れなかったときにも、悩むことがありました。
ですがこうした不安を感じても、気持ちを切り替えて勉強するようにしていました。また、「絶対できる」と信じるようにしていました。
大学受験はメンタルを試されます。「強い気持ち」をもち、不安がよぎっても「自分なら大丈夫。できる」と信じましょう。
逆に「これからまた1年の時間があるから、休みながら勉強しても大丈夫」のように考えていると、成績は伸びません。一般的に「浪人生は現役以上に伸びない」といわれるのは、浪人生がこうした気持ちになりやすいためです。
常に不安や緊張を感じていると、体調を崩してしまうことがあるため、「何とかなる」と楽観的に考えることも必要ではあります。ただ、ずっと楽観的に考えてしまうと、伸び悩む浪人生になってしまいます。
現役生は受験に間に合うように必死で勉強しています。それに負けない気持ちをもって勉強することがとても大切です。私の場合は「現役のときに合格できなかった第1志望の大学は最低ライン、できればそれ以上の大学を狙う」という気持ちをもっていました。
浪人生の生活スケジュール
浪人をしたときに、私は大手予備校の「河合塾」に入ることにしました。
私は「独学で勉強するほうが自分に向いている」と思っていたのですが、両親が「家にずっといるのは親としても大変だから、予備校に行きなよ」と言ってくれました。そのときには正直なところ「面倒だな」と思ったのですが、今思うと学費を出してくれた両親にはとても感謝しています。
予備校に通うことになった私は、毎朝7時頃に起きて予備校に通う生活が始まりました。予備校での生活スケジュールは高校と似ています。
こうしたスケジュールで勉強していました。ただ、私は「講義を聴くよりも、参考書と問題集で勉強したほうが効率がいい」と思うことがあったので、ときどき講義を休んで自習室や図書館で勉強していました。
これは決して「河合塾で教えてくれる講師の質が低い」というわけではありません。河合塾の講師はとても分かりやすく教えてくれるので、「自分に合う」と思ったら講義を受けるほうが良いです。私は「結局のところ、勉強をして学力が伸ばすことができれば良い」と考えていました。そのため、より自分に合っていた独学を中心として勉強していました。
また、私が講師をしていた塾にも浪人生の生徒がいました。こうした生徒の例も挙げておきます。
塾に通っていた浪人生は、このようなサイクルで勉強していました。
予備校の講義は高校よりも自由度が高く、私のように講義を休むことができてしまいます。ただ、基本的には講義をしっかり受けて、生活リズムを作るほうが良いです。「自分で自由に勉強する」というスタイルで勉強しようとすると、人によっては生活リズムを上手く作ることができず、学力が伸びにくくなってしまうことがあります。
使った教材は「現役時代の教材+α」
私が浪人時代、現役時代に使っていた参考書と問題集に加えて、「難しめの問題集」と「志望校より少しレベルが高い大学の過去問」を使いました。あまり教材を増やすことはせず、理解しきれていない部分を埋めることを中心に行いました。そのため、何度も何度も「復習」をしていました。そして志望校の問題に余裕をもって対応できるように、ワンランク上の大学を狙って問題演習をしていました。
浪人して志望校に合格するためには、「現役のときに何が足りなかったのか」を考えることが大切です。「苦手な部分が残っていた「より難しい問題を解ける必要があった」「普段は解けるのに、プレッシャーに押しつぶされてしまった」など、人によってさまざまな原因があります。これを自分で振り返り、対策することが大切です。
私は河合塾に通っていたものの、正直なところ河合のテキストをあまり活用していませんでした。予備校のテキストはとても質が良いため、メインの教材として活用できるものです。私の場合は、使い慣れていた教材を引き続き完璧にマスターするようにしました。
私にとっての予備校は講義の内容そのものよりも、「毎日行くことでのペース維持」「予備校でできた友達と話すこと」に意味があったと思います。
私は浪人したときに高校時代の友達と会う機会が少なくなり、予備校でできた友達と話をしていました。あまり遊びすぎるのは良くありませんが、友達と話すことで不安やストレスを和らげることができていたと思います。
最も気をつけることは「モチベーションの維持」
浪人生活で一番気をつけるべきなのが、「モチベーションの維持」です。
浪人生は現役のときに勉強していたため、ある程度の基礎力・応用力ができ上がっています。そのため勉強することに対して「もう分かっている」という油断をしてしまいやすいです。そしてこれが続くと、受験勉強へのモチベーションが下がってしまいます。
浪人生として学力を伸ばすためには「いかにモチベーションを上手く保つか」がとても大切です。私は次の3つに気をつけていました。
- 「ペースメーカー」を作る。
- 意識して休む日を作る。
- 「悔しさ」や「不安」を思い出す。
「ペースメーカー」を作る
上でも紹介したように、浪人生は「生活リズム」を保つ必要があります。そのためには、何かの形で「ペースメーカー(勉強のペースを保ってくれるもの)」を作ると良いです。ペースメーカーとして使えるものは、次のようなものがあります。
- 予備校に毎日通う。
- 定期的に開催される模試を受ける。
- 進研ゼミやZ会など、毎月届く通信教育を利用する。
- 自分で勉強する時間帯を決める。
このように毎日や一定期間ごとに来るイベントをペースメーカーにすると、勉強にメリハリをつけやすく、モチベーションを保つことができます。私がとくに意識していたのは「模試」で、次に「予備校」でした。
模試は2〜3ヶ月ごとに開催されており、積極的に受けていました。日々の勉強でインプットしたことを模試でアウトプットすることで、より知識を確実なものにすることができます。また、「模試までの2ヶ月間、しっかり勉強しよう」と思うことで、勉強の学習効果を高めることができます。
私の場合、模試を受けるためには都市部に出る必要がありました。そのため「受けに行くのが何となく楽しかった」ということも、模試をペースメーカーにしていた理由です。
また、「今日も予備校に行かないと」という気持ちは、良いペースメーカーになってくれます。
予備校に行かない場合は、通信教育を利用すると良いです。毎月1回教材が届くことに加えて、添削問題を提出する必要があるため、勉強のペースを保つことができます。通信教育は月1万円ほどからでも受講でき、たくさんの教材が届きます。
独学で勉強する場合は「朝9〜12時と13〜18時・20〜22時に勉強する」のように決めることで、ペースを保ちやすくなります。時間帯を決めておかないとついだらけてしまいやすいので気を付けてください。
意識して休む日を作る
浪人生は、平日・土日とも勉強を続けてしまうことがあります。ただ、ときには意識して休むほうが良いです。勉強をする日と休みの日を区別することで、メリハリをつけることができるようになります。しっかり休むほうが自分の身体を回復できて、気持ちもリフレッシュすることができます。ずっと勉強し続けているとだらだらと勉強するようになってしまい、逆に効率が落ちてしまいます。
そのため、「日曜日は朝だけ勉強するようにして、あとは思いきり遊ぼう」のように決めておきましょう。私は中途半端に勉強して、あまり十分に休めずに過ごしてしまうことがときどきありました。ぜひ気をつけてください。
「悔しさ」や「不安」を思い出す
浪人生活でモチベーションを保つ方法として、ときどき現役時代の悔しさを思い出したり、「浪人して合格できなかったらどうしよう」という不安をイメージしてみたりすることも効果的です。
こうしたマイナス感情は、その気持ちにずっと引っ張られてしまうと良くありません。ただ、マイナスな気持ちをバネにすれば、逆に自分を「頑張ろう」とふるい立たせる材料になります。
私は「浪人して不合格だとさすがにまずい」と思い、モチベーションを保って勉強していました。ときには不安に落ち込んでしまいそうになることがありましたが、「いや、落ち込んでいられない」と思ってまた勉強していました。
浪人生活で得たこと・学んだこと
浪人すると、現役で合格した同年代の友達は先に大学生活を満喫していて、うらやましく思うことがあります。そして大学を卒業するときも、高校時代までの友達とは1年遅れて仕事を始めることになります。
ただ、私は浪人したことについて「人生でとても大きなマイナスだった」とは思っていません。むしろ浪人することで妥協せずに第1志望の大学に合格できたので、「浪人して良かった。頑張って良かった」と思いました。
大学に入学すると、同じように浪人生活を経て大学生になった人はたくさんいます。また、現役で入学した1歳年下の人とも友達になることができます。そのため、「高校の友達に遅れを取った」と思う必要はありません。
1年は長い人生で見れば小さな差です。もちろん現役で志望校に合格できれば、それに超したことはありません。また、現役のときから「浪人がそれほど悪くないのなら、もう1年勉強するのも良いか」と考えるのもおすすめしません。
ただ、浪人することになった以上は前向きに考えて、「現役の人たちとはまた違った経験ができる」と考えておきましょう。そして満足のいく浪人生活を送れるように、頑張ると良いです。自分で「浪人時代を意味のある時間にしよう」と考えて勉強すれば、1年後は「浪人での経験は有意義だった」と思えるはずです。
浪人時代を振り返ると、たしかに大変ではあったのですが、とても意味のある1年だったと思います。
私は理系だったのですが、数学・物理・化学は浪人時代に自信がつき、化学は特に好きな科目になりました。「大学受験の勉強はあまり意味がない」ということがよく言われますが、「学問の面白さ」を何となく感じることができた1年でした。
気持ちを保ち、有意義な浪人生活を
私の浪人生活の体験談は以上です。「浪人生は伸びない」ということは全くなく、あなた自身にかかっています。現役時代に満足のいく成果を出せなかった悔しさをバネにすれば、モチベーションを保って勉強を続けることができるはずです。ぜひ有意義な浪人生活をして、「浪人して良かった」と思えるように頑張ってください。