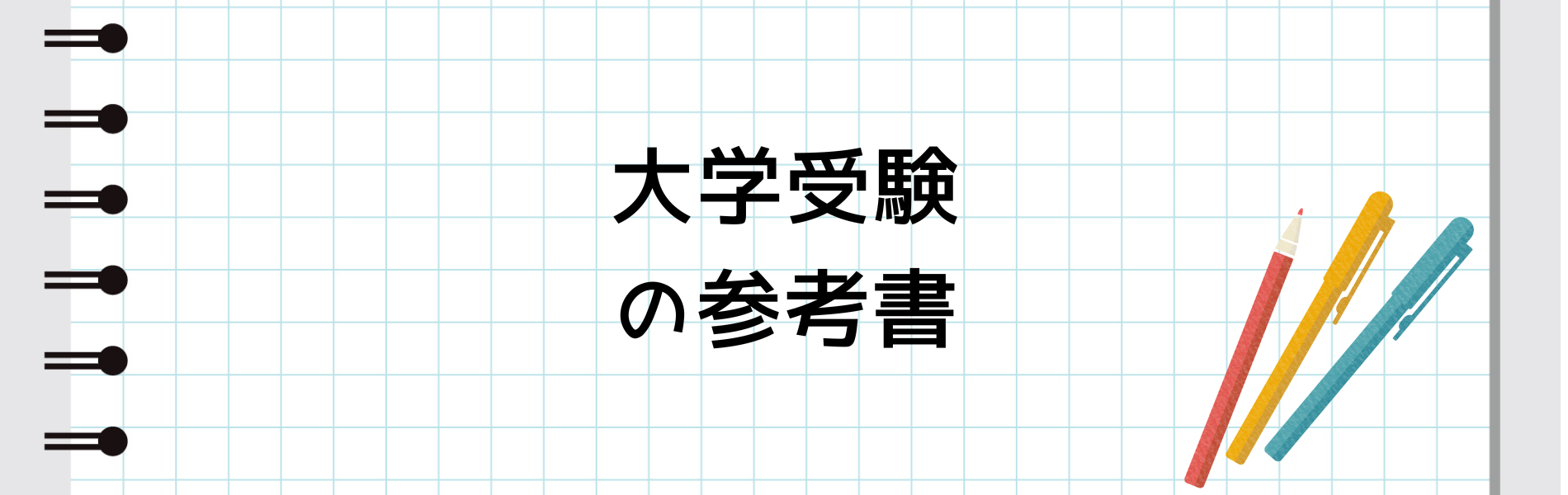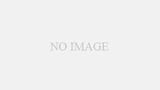※このページはプロモーション(広告)を含みます。

お子さんが、数学の偏差値が低いと悩んでいる。
そんなとき、親としてどうサポートすれば良いのか、迷いますよね。
特に偏差値が30や40のまま、なかなか上がらない状況だと心配になるものです。
この記事では数学の偏差値が上がらない理由と、その克服方法に焦点を当てています。
お子さんが「数学、もうちょっと頑張ってみようかな」と思えるような、ポジティブなアプローチを紹介しています。
数学の偏差値を向上させるには、具体的な対策と少しの励ましが必要。
筆者もたくさんの生徒さんを教えてきましたが、数学で伸び悩む生徒さんの多くに当てはまる原因はあり、その解決策もあると感じています。
この記事を通して、お子さんの数学学習を一緒に応援しましょう!

原因と対策方法がわかれば、数学を克服する道も見えてくるはず。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
数学の偏差値が低いときの原因5つ

お子さんの数学の偏差値が30〜40で伸び悩んでいる場合、まずは下の5つに当てはまらないかチェックしてみると良いです。
- 中学校で習う内容があやふや。
- 教科書の例題が解けない。
- 公式を覚えていない。
- 計算練習が足りない、雑に解いている。
- 前に習った内容を忘れてそのまま放置。
上の点はお子さんが何となくわかっていても、意外となかなかできないもの。
それぞれのポイントについて解説します。
中学校で習う内容があやふや
高校の数学は、中学の数学が理解できている前提で進みます。
そのため、まずは中学校の内容を理解することが必要です。
- 基本の計算がスムーズにできるか。
(分数・プラスマイナス・式の展開・連立方程式・ルートなど) - 三平方の定理・解の公式・因数分解の公式など、中学校で出てくる公式を覚えているか。
そこまで高いレベルは必要ありませんが、お子さんが上のことを「まあできるかな」と思えない場合、中学内容を全体的に振り返る必要があります。

高校でも、中学校で習った計算・公式はよく出てくるもの。
理解していないと、いつもそこでつまずくことになります。
逆に言えば、中学数学の抜けをなくすだけでも、高校数学の学習もある程度はスムーズになるはずです。
教科書の例題が解けない

中学内容は理解できていても、高校の教科書を理解できていないと、当然ながら点数は伸びません。
次は、高校の教科書の例題(応用例題も含む)を解けるかチェックすると良いです。
ここで気をつけたいのは、「解答を見ないで解けるかどうか」が確認の基準ということ。
偏差値が低い原因は、問題が解けないから。
お子さん自身は「わかっている」と思っていても、いざ問題が出されると、「あれ、どうやって解くんだっけ・・」となることは多いものです。
何も見ずに問題を解けるよう、ノートに書いて練習する必要があります。
公式を覚えていない

公式を覚えていないと、そもそも問題に取りかかる段階でつまずいてしまいます。
公式は何となくではなく、いつ聞かれてもすぐ答えられる状態にしておくことが大切。
また、公式は使い方も身につける必要があります。
上でも触れたように、「公式を使って、教科書の例題・練習問題を解けるか」が基礎を身につけられている基準。
公式を覚えただけでは解けない問題もありますが、まずはこれまで習った公式を暗記していることが第一歩です。
今習っている分野の公式をひと通り覚えたら、以前に習った分野の公式も確認しましょう。
計算練習が足りない、雑に解いている

数学の問題は理解できても、反復練習をしないとスムーズに解けません。
また、ひとつひとつの問題を雑に解いていると、いつも数字が違う、正解にたどりつけない、ということになります。
単純な計算は退屈なもの。
ただ、1日10〜15分でも計算のトレーニングをすると、数学の伸びがぐっと変わります。
前に習った内容を忘れたまま放置
英語や国語では、単語・文法の知識は科目全体を通して使うため、1度覚えたら忘れにくいものです。
一方、数学は分野ごとに考え方や公式が違うため、以前に習った内容でも、時間が経つと忘れてしまうことがよくあります。
「数2Bに入り、数1Aの内容をキレイさっぱり忘れてしまった」ということはよくあり、そのまま放置してしまうと偏差値は伸びません。
いま習っている分野も大切ですが、これまでに学習した内容も計画的に復習する必要があります。

まずはお子さんに何が原因で数学の力が上がらないのか、ここまでの5つで思い当たるものを考えてもらうと良いですね。
数学の偏差値を50に上げるには?
ここまでの原因を踏まえて、数学の偏差値をまず50にするには、お子さんに次のポイントを教えてあげてみてください。
中学内容であやふやな部分をまず理解
まずは中学校の内容を先に復習しましょう。
- 「分数の計算でいつもつまずく」
- 「プラスマイナスが、ずっとあやふやなままだった」
- 「グラフがよくわかっていない」
のように、理解できていないと思う中学の内容をメモに書き出し、順番に復習すると良いです。
数学が苦手な多くの人は、「今さら中学校の問題なんて、、やらなくても大丈夫!」と油断して、復習しようとしません。
ただ、お子さんが思っている以上に中学内容が抜けていることは多いため、伸び悩んでいる場合は振り返っておくべき。
▲【楽天ブックス】改訂版 中学校3年間の数学が1冊でしっかりわかる本
使う教材は、残っていれば中学校の教科書やワークで十分です。
もし捨ててしまった場合は、インターネットで探せる動画や、上のようなまとめの問題集で補強すると良いでしょう。
中学生のときは難しく感じた内容も、今ならお子さんも「なんだ、意外とわかるな」と感じることも多いはずです。
教科書の例題を全て解けるようにする
中学の内容を補強できたら、次は教科書の例題を解けるようにします。
今習っている分野で、教科書の例題を1番始めの問題から解いてみましょう。

このとき例題のすぐ下にある解答を確認するだけではなく、必ず紙に式を書くようにします。
実際に解いてみると、
- 解けない・わからない。
- 答を見れば、理解できて解ける。
- 答を見ずに、すぐ解ける。
という3パターンになるはず。
そして全ての例題で、答を見ずにすぐ解ける状態にすれば、基礎は身についているということです。

数学が苦手なお子さんでも、各分野の最初に出てくる問題は解けると思います。順番に例題を解き、自力で解けない問題は、まず解答を見て理解しましょう。
そのあともう1度何も見ない状態で解き、スムーズに正解できれば、その問題は初めて「理解できた」と言えます。
時間はかかりますが、ひとつひとつの例題を自力で解けるようにしていけば、その分野の基礎固めは十分。あとは忘れないよう、見直し・復習(書いての解き直し)をします。
また、余裕が出てきたら学校で配布されている問題集のA問題、さらにB問題も解くと、偏差値50には届くはずです。
公式を全てしっかり覚える
教科書の例題を解くときには、公式が出てきます。
「あ〜、あったな」という感じではなく、ぱっと出てくるように覚えておくことが大切。
ちなみに、数学の公式は「なぜその公式が出てくるのか」という導き方があり、理解しておくと納得しやすくなります。
ただ、公式の証明は難しいこともあるため、偏差値50に届かない状態ではあまり気にしなくても構いません。
問題を解くときていねいに計算する

お子さんが計算ミスをよくしてしまう場合、計算練習をすると良いです。
因数分解や式の展開など、苦手と感じる計算は、まとめて反復するほどスムーズにできるようになります。
ただ、中には単純な計算を甘く見てしまい、「計算練習に時間を取れない、取る気がしない」という人もいます。
この場合、教科書の例題を解くときの計算を、ていねいにするよう意識してください。
「ていねい」というのは、学校の先生や予備校の先生の文字や書き方を真似すると良いです。
また、できれば1対1や少人数の塾で、先生にノートをチェックしてもらうのがおすすめ。
ひとつひとつの計算にきちんと取り組むことでも、計算力を上げられます。
以前に習った分野を復習する
偏差値を上げるには、いま習っている分野を理解することも必要ですが、復習も大切。
優先して復習するべきなのは、
- 中学内容
- いま学校で習っている分野
の2つです。
ただ、まだ時間があるなら、以前に習った分野も復習(教科書の例題を解く)すると良いでしょう。
特に弱いと感じる分野があれば優先的に解き直すのも良いですし、数1Aの最初から全て復習するのも良いでしょう。
ただ、量が多すぎて挫折しないよう、「これなら終われそう」という見通しを立てて始めると良いです。

原因がわかり、その対策がわかったら、あとは勉強するだけ。
とはいえ、計画的に進めることがとても大切です!
数学の勉強時間を取り計画的に学習

原因がわかり、対策の仕方がわかったら、あとは計画的に勉強することも大切です。
「数学の偏差値がやばい!俺は今日から変わる!」と気合いを入れても、3日後には「やっぱりダメだ・・」と心が折れてしまうことはよくあります。
お子さんが挫折する可能性があることを頭に入れて、先に無理のない学習計画・準備を整えておきましょう。
また、最近はこうした計画の作成・進み具合をチェックする「学習管理」に力を入れている塾も多いため、考えてみるのもひとつの選択肢です。
1日15〜30分でも数学を勉強しよう

数学が苦手なお子さんは、いきなり「1日3時間やるぞ!」と意気込んでも、残念ながら長続きしないことがほとんど。
継続して勉強することが大切なため、最初は無理せず15〜30分から始めると良いです。
これくらいだと「もう終わり?」と、お子さんも親御さんも物足りなく感じるかもしれません。
ですが、「もう少しできるのにな」と思うくらいの気持ちを残しておくほうが続けやすいです。
そして慣れてきたところで40分や50分、さらに1時間に伸ばせば、無理なく勉強時間を増やせます。
抜けがないよう順番に理解しよう

数学は「ひとつ理解できると、次もわかる」というように、階段を上るイメージで進みます。
逆に言えば「ひとつ理解できないと、その後も理解しにくくなる」ということになるため、教科書の例題は必ず抜けがないよう順番に理解することが大切です。
「この問題はよくわからないから、飛ばして先に進もう」と考えても、後半に進むほどあやふやな理解になりがち。
教科書の例題でわからない問題が出てきたら、友達や先生など、周りの人に聞くと良いです。
質問しにくければ、塾を活用するのも良いでしょう。
以前の分野の復習を計画的に進めよう

以前に習った分野の復習をすると、より偏差値は伸びやすくなります。
教科書の例題を順番に復習すると良いですが、学年が進むほど振り返るのが大変です。
「教科書の例題なら、ひと月に2分野ずつなら何とか復習できそう」のように、無理なく進められるペースで計画的に進めましょう。

最後に、やはり塾を利用することは考えてみるべき。
無理にお子さんを通わせても効果は薄いですが、数学の苦手克服という目的にピンポイントで役立つ塾を利用すれば、かなり学習効果は期待できます。
数学の苦手克服にはできれば塾の利用を

原因と対策がわかったら、自分で計画を立てて勉強することは一応できます。
ただ、できれば塾を活用すると、やはり無理なく勉強できるものです。
数学が苦手なお子さんは「頑張ろう!」と思っても、なかなか続けられないもの。
最近は自習も効率的・効果的に進められるよう、下のような学習管理に力を入れる塾が増えています。
- 学習計画の作成
- 見直し
- 管理(進度チェックや確認テストなど)
- 質問対応
大学受験は大手の塾や予備校を考える人も多いですが、ブランドだけでなくお子さんに合うサービスかを確認することも大切。
数学の苦手克服にぴったりな、おすすめの塾を紹介します。
数学専門のオンライン塾MeTa

MeTa(メタ)はオンラインで学べる、数学が苦手な人向けの塾。
オンラインなので塾へ行く気になれないお子さんも始めやすく、先生は「数学嫌いな生徒さんに共感できるか」を重視して採用されています。
授業では単に各分野の解説だけがされるのではなく、生徒さんの手元(ノート)を確認しながら進行。
数学が苦手なお子さんは、間違った考え方・計算のクセをつけてしまいがちです。
MeTaなら問題の解き方の流れや数式の書き方まで、しっかりチェックしてもらえます。
さらに、授業とは別に毎月の学習計画(3日ごとのやるべきこと)を作成、LINEでいつでも質問可能と、授業がない日もしっかり勉強できるようサポートが充実。
お子さんの数学を何とかしたいと思ったら、体験授業を受けてみるのもおすすめです。
(詳しい解説はこちら)
▶️数学苦手克服塾MeTa、今まで伸びなかったけど本当に上がる?
先生が東大生でわかりやすい!東大先生

東大先生は文字通り、東大生の先生がオンラインで1対1指導をしてくれる塾。
「東大生の先生なんて、うちの子が理解できるのかな・・」と思うかもしれません。
ただ、根本的なところから正しく理解している東大生だからこそ説明も納得でき、「圧倒的にわかりやすい」と評判です。
東大生の先生は常識・マナーをしっかり身に付けている人も多く、上から目線ではなくお子さんに寄り沿うようなスタンスでていねいに教えてもらえます。
さらに東大先生は学習管理にも力を入れていて、綿密な学習計画も作成。
上で紹介した苦手克服の方法や復習の計画も、しっかり日々の学習に組み込んでくれます。
さらに日々の勉強での質問も、チャットで東大生の先生が回答、オンライン自習室での勉強もカリキュラム(学習計画)に組み込まれるため、自習時間もしっかりと確保。
最初の無料学習相談も好評なため、合うかどうかわからないと思ったら、まずは相談してみると良いですね。
まとめ
数学の偏差値が上がらない、なかなか伸びないというお子さんには必ず原因があり、その対策もまたあります。
「今でしょ!」ではありませんが、ここで紹介した原因で当てはまるものがないかをチェックして、できることから始めてみましょう。
ただし苦手な科目を自力で進めるのはとても大変なため、できれば塾も活用するとよりスムーズ。
オンライン塾はお子さんが移動する負担がないため利用しやすく、ここで紹介したように、最近は数学に強いサービスもあります。
お子さんをぜひ、しっかりサポートしてあげてくださいね。

数学は理系・文系どちらでも大切な科目。
苦手を克服することで志望校の幅も広がり、論理的に考える力も身につきます。
対策するなら早いほうが挽回しやすいので、ぜひお子さんに教えてあげてくださいね!