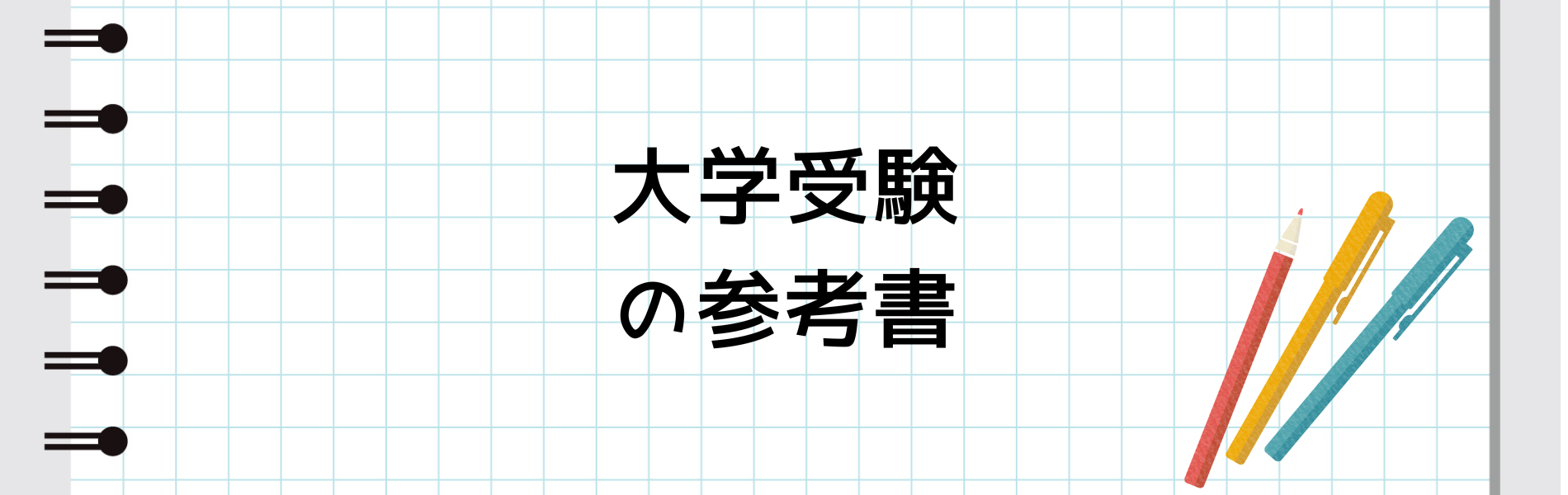※このページはプロモーション(広告)を含みます。

「物理」は、多くの人が苦手になりやすい科目です。文字がたくさん出てきて、苦手だと公式をどう使えば良いかも分からないことが多いです。
ただ、物理は正しい勉強の仕方で学べば、点数を取りやすい科目でもあります。そこでここでは、「物理が苦手な場合の勉強法」について紹介します。物理の苦手を克服して、全体的な点数を底上げしましょう。
物理は「イメージ」が大切
物理は「ボールが移動している」「バネについた球が振動している」など、問題ごとに何らかの「現象」が起きています。まずは問題でどのようなことが起きているのかを「イメージ」することが大切です。
問題を解くときに、すぐ式を立てようとするのではなく、「この問題では、ビルの上からボールが斜めに向かって投げられているのだな」のように、イメージを働かせてください。
そしてそれを、「図」に描くと良いです。図に描くことで「問題に出てくる物体がどんな動きをしているか」が分かりやすくなります。そして、式も立てやすくなります。
物理では、さまざまな公式が出てきます。しかしやみくもに公式に当てはめようとしても、問題を解くことはできません。「現象をイメージして、それを式として表す」という流れで解くことが大切です。
逆にいえば、きちんと現象(問題で登場する物体の動き)が想像できれば、さまざまな問題に対応できます。
公式を暗記せず「どう成り立っているか」を理解する
物理の公式は、覚えても上手く使いこなせないことが多いです。それは「どんな場合に公式を使えば良いか、分からないため」です。
そのため物理の公式は、「導き方」を理解しておくと良いです。自分で導き出せるようになるとより良いですが、1度でも公式の導出方法を理解すると、「こういう仕組みで公式が出てきているのか」と分かるようになります。すると問題を見たときに、公式に当てはめやすくなります。
公式の導き方は、教科書以外にも参考書などで解説されています。導出の説明は読み飛ばしやすいですが、きちんと読んでおくと良いです。
数学や化学など、ほかの理系科目にもいえることですが、「根本的な部分」をきちんと理解していると、応用が利くようになるのです。
用語をきちんと理解する
物理には「運動方程式」や「エネルギー保存則」「ドップラー効果」など、さまざまな用語が出てきます。こうした用語をきちんと理解することで、物理の問題を解きやすくなります。
・運動方程式は「物体が力を受けて運動するときに立てる式」
・エネルギー保存則は「力を受けない場合に、位置エネルギーと運動エネルギー、バネのエネルギーの合計が一定になること」
上のように、それぞれの用語が「何を表したり、どんなときに立てたりする式なのか」を理解しておきましょう。
こうして用語を理解しておくと「これは運動方程式を使う問題だ」「この問題では、エネルギー保存則が成り立つな」のように、問題を見てすぐに現象を理解することができます。
グラフの読み取りに慣れる
物理では「グラフ」がよく出てきます。「v-tグラフ(速度と時間のグラフ)」や「x-tグラフ(位置と時間のグラフ)」など、さまざまなグラフがあります。
グラフは「縦軸」と「横軸」を確認して、「何の関係を示しているのか」についてきちんと読み取りましょう。また、「囲まれる面積」が重要な場合もあります。v-tグラフの場合、囲まれる面積は「移動距離」を示します。
グラフが問題に出てきたら、「何の関係を示しているのだろう」としっかり考えましょう。ひとつひとつのグラフでこのように考えていると、読み取りに慣れることができます。
物理のセンスを磨くために適した参考書
物理の教科書は正直なところ、分かりにくいです。教科書は厳密な説明を意識しており、複雑な用語や記号がたくさん出てきます。それが逆に、分かりにくさの原因となっています。
また、学校でよく配布される「セミナー物理」などの問題集も、問題の質は良いものの解説が分かりにくいです。これを使っても単に問題を解くだけになってしまい、物理のセンスを磨くことはできないのです。
物理のセンスを磨くなら、書店で売っている「参考書」で学ぶほうが良いです。初心者におすすめの参考書を紹介します。
漆原晃の物理基礎・物理が面白いほどわかる本(中経出版)
大手予備校の人気講師、漆原晃先生による物理の基本的な参考書です。とても話し言葉の読みやすい文体で説明されており、現象のイメージ方法や式の立て方を学ぶことができます。これだけで物理を完成させることはできませんが、ひと通り読むと物理の苦手意識がなくなったり、好きになったりするはずです。
宇宙一わかりやすい高校物理(学研)
可愛いイラストと図解を多用した参考書。また、説明も堅苦しくないため、スムーズに読み進めることができます。「確かに分かりやすい」と多くの受験生に評判です。問題も用意されているため、学んだ知識を問題で実際に活用することができます。
橋元の物理をはじめからていねいに(東進ブックス)
分かりやすく物理を教える人気講師として有名な橋元先生による参考書。こちらもとても分かりやすいです。「物理はイメージ」というコンセプトを掲げており、問題で起こっている現象を分かりやすく解説してくれます。
上の「面白いほどわかる本」「宇宙一分かりやすい」「はじめからていねいに」の3つは、書店で確認してどれかひとつを購入すれば大丈夫です。説明が自分に合うと思ったものを選んでください。
物理のエッセンス(河合出版)
物理のエッセンスは基礎レベルから使えて、参考書としても問題集としても活用できます。分かりやすい説明と見やすいレイアウトに加えて、収録されている問題の質が非常に高いです。まさに「エッセンスを含んだ問題」がたくさん掲載されており、ひと通りマスターすると、さまざまな物理の問題が解けるようになります。
初心者でも理解できますが、上の3冊に比べると少し説明を省いている面があります。物理のエッセンスの説明を理解できるなら、上の3冊よりもこちらをおすすめします。到達できるレベルが高いです。
スタディサプリの物理講座

講義形式で学ぶほうが向いているなら、月1,078円(税込)で利用できる「スタディサプリ」というサービスはおすすめです。スタディサプリはプロの予備校講師による授業を、スマホの動画で学ぶことができます。物理についても講座が用意されており、分かりやすい授業で学ぶことができます。
スタディサプリの授業は15分や30分など、ポイントを押さえて短くまとまっています。そのため空き時間に講座を学ぶことができ、効率良く時間を使うことができます。スタディサプリは最初に14日間の無料おためしができるため、まず見てみるのはおすすめです(※無料期間は申込日が1日目)。
繰り返し学び、理解を深める
参考書を用意したら、繰り返し復習して理解を深めましょう。1度読んだり解いたりしただけでは、まだ理解があいまいなはずです。そのため3~5回は繰り返し学び、しっかりと知識を定着させましょう。
こうして参考書をマスターすると、模試や実力テストなどの問題を解くときに、物理の現象がイメージできるようになっているはずです。そして、物理に対する自信がつくはずです。
基礎が身についたら、問題演習を繰り返す
物理は基礎をしっかりと身につければ、さまざまな問題に対応しやすくなります。参考書をマスターしたら、その知識を活用して問題を解きましょう。おすすめの問題集も2つ紹介しておきます。
良問の風(河合出版)
良問の風はスタンダードな入試問題を網羅した問題集です。物理は長らく「重要問題集」が評判となっていましたが、良問の風もとても良い問題集です。
良問の風は上で紹介した「物理のエッセンス」を執筆した、浜島先生という方が作成しています。そのため、物理のエッセンスで学んだあとに使いやすいです。もちろんほかの参考書で学んでいても、スムーズにつなげることができます。
浜島先生が選ぶ問題の質はとても優れており、解きながら物理への理解を深めることができます。解説もていねいで、別解として「より早く解けるテクニック」などが紹介されています。繰り返し解くたびに、味わいのある問題集です。
物理・重要問題集(数研出版)
重要問題集は、「物理の問題集といえばこれ」と評判になっている問題集です。物理の入試で出題されやすい典型問題を、しっかりと網羅しています。
問題の質は、非常に良いです。解説もていねいですが、「新たな発見」や「知的好奇心」を満たしてくれる要素はあまりありません。質の良い問題をどんどん解いて、演習を積み重ねたい場合におすすめです。
ちなみに私が受験生の頃は、良問の風を使っていました。ただし正直なところ、物理でしっかりと完成させたのは「物理のエッセンス」と「過去問5年分」「模試の問題」の3つです。これでも十分、入試問題に対応できます。物理のエッセンスにはレベルの高い問題も収録されており、これをマスターすると難関大学(旧帝大など)の入試問題も解けるようになります。
ただ、この勉強は全ての人に当てはまるわけではありません。そのため良問の風や重要問題集を確認して、自分に合うと思ったほうを使って問題演習をすると良いです。
正しい勉強で、物理の苦手を克服しよう
ここでは「物理が苦手な場合の勉強法」について紹介しました。物理で最も大切なのは、やはり「イメージ」です。いつも現象をイメージして、自分で図を描くよう心がけてください。その上で用語や公式を理解すれば、立てる式を自然と思いつけるようになります。
物理は問題で身近な物事を扱うこともあるため、分かるようになると面白く感じやすいです。正しい勉強方法で、物理の苦手を克服しましょう。