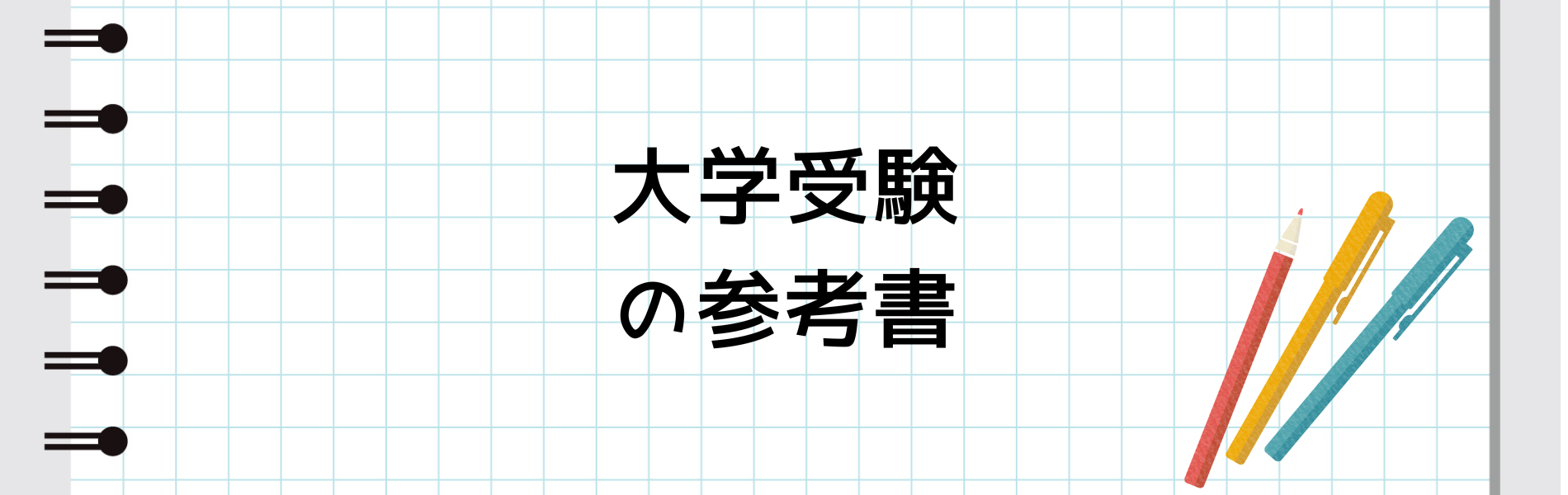※このページはプロモーション(広告)を含みます。

数学は大学受験において、とても大切な科目です。センター試験でしっかり得点できると、受験が有利になります。
ただ、場合によっては「センター試験の数学対策を、どうやって進めれば良いか分からない」ということがあると思います。そこでここでは「センター数学の対策方法」について紹介します。きちんと正しい対策をすれば、センター本番で8~9割を得点することは十分できます。
なお、センター対策にもおすすめの、偏差値・点数アップに直結する教材を別ページで紹介しています。こちらも合わせて参考にしてください(親子で相談するのがおすすめです)。
センター試験の数学対策、3つのポイント
センター数学は「問題レベルは標準的だが、問題数が多い」という特徴があります。これを踏まえてセンター試験の数学対策では、大きく分けて3つのポイントに気をつけて対策する必要があります。
基礎力をしっかり固める
センター数学の問題は、教科書の問題を解けるようになるだけでは得点できません。「センターの問題は易しい」という言葉を真に受けると、まったく点数をとれない可能性があります。
確かにセンターや大学入試の問題は、教科書の知識で解くことができます。しかし「問題を解くときに、知識をどう活用するか」を身につけておく必要があるのです。
そのため教科書だけでなく参考書や問題集で勉強して、「解法(解き方のパターン)」を習得しましょう。これを数1A・2Bの全範囲について行う必要があります。
解くスピードを上げる
センター数学は問題数が多いため、ゆっくり解いていると時間が足りなくなってしまいます。そのため、基礎~標準レベルの問題を解けるようになったら、「解くスピード」を上げるよう意識してください。テキパキと問題を解けるようになれば、センターでも全ての問題を解き切ることができます。
スピードを身につけるためには、「反復練習」が大切です。標準レベルの問題をたくさん、繰り返し解くと、知識がしっかりと定着します。すると公式や解法をさまざまな場面でパッと使えるようになり、問題を速く解けるようになります。「知識の習得→反復練習」で、スピードを身につけましょう。
正確に解く
問題を速く解くことができても、ミスをしたら意味がありません。特にセンター試験は「マーク式」であり、「答が合っているかどうか」だけが重視されます。
ミスを防ぐためには、次の3点を意識すると良いです。
- 計算を甘く見ず、最後まできちんと解き切る。
- 自分で読みにくい字を書かず、はっきりていねいに書く。
- 計算をし終わったら、確認をする。
これらを心がけると、ミスを減らすことができます。数学の問題を解くときにいつも意識すれば、計算練習を兼ねることができます。こうしたことを日頃から積み重ねておくと、センター試験本番で役立ちます。
基礎固めをするために適した参考書・教材
センター試験の問題を解けるように基礎を固めるためには、次に紹介する方法がおすすめです。どれも効果的ですが、人によって取り組みやすい方法が違うはずです。自分に合ったやり方で基礎固めをしてください。
会話調の参考書
まずは「会話調で解説された参考書」を利用する方法です。数学が苦手な場合や文系の場合には、こうした参考書が分かりやすいです。こうした教材は予備校講師が執筆していて、講義で話しているような文体で解説がされています。そのため、内容がすっと頭に入りやすいです。
解説や問題が並んでいる参考書や問題集は、「まとまっている」という面では良いです。ただ、「取り組みやすさ」の面からすると不親切です。
会話調の参考書は「全ての問題や項目について、解説されているわけではない」というデメリットがあります。ただ、重要なポイントは押さえられており、数学が苦手な場合にまず必要なことを学ぶにはちょうど良いです。
「センター試験数学の点数が面白いほどとれる本(中経出版)」「◯◯が面白いほどわかる本(中経出版)」はおすすめです。両方とも「分かりやすい」と評判の講師が執筆しています。
スタディサプリの「スタンダード」「センター試験対策講座」

リクルートが提供している「スタディサプリ」というサービスを使うのも、センター数学の対策に効果的です。スタディサプリは月1,078円(税込)で利用でき、「予備校講師による動画授業」をスマホで見ることができます。講座に合わせたテキストも用意されており、ダウンロード・印刷が可能です。
スタディサプリは講座のレベルが分けられており、「スタンダード」「ハイレベル」「トップレベル」の3段階があります。また、これとは別に「センター対策講座」も用意されています。
センター対策講座はポイントを絞って解説しているため、まずは「スタンダード」で基礎を身につけると良いです。そして高3の8月や秋に入ってから、「センター対策講座」を学ぶと効果的です。
講義形式で学びたい場合は、スタディサプリがおすすめです。料金がとても安いにもかかわらず授業の質がとても高く、数学の基礎固めに最適です。
黄チャートの「レベル3までの例題」
淡々とした問題構成に飽きないなら、「黄チャート(数研出版)」もおすすめです。受験数学の定番参考書として知られており、特に「例題」はとても良い問題が多いです。
センター試験レベルの学力を身につけたい場合、難易度レベル5段階のうち「レベル3」までの問題を、しっかり身につけると良いです。取り組む問題は「例題」のみで構いませんが、スムーズに解けるまで反復しましょう。黄チャートは分厚いですが、レベル3までなら問題数はそれほど多くありません。
センター数学の問題は、基礎~標準の解法を組み合わせて構成されています。つまり噛み砕けば、黄チャート例題の解法でほぼ解くことができます。
夏までに基礎を身につけておく
まだ基礎を固めていない場合、上の勉強は高3の7月末までに終えておくとベストです。受験期間の後半に入ってから基礎固めに取り組むと、センター試験本番までに対策が間に合いません。
また、理系で国公立を狙う場合、上の勉強だけでは足りません。自分の志望校に合ったレベルの基礎固めをすれば、センター数学に対応する基礎力も身につけることができます。
ちなみに「基礎を固める」とは、「教材に出てくる問題ほとんどを見てパッと解き方が思いつき、すぐに解ける」ということを意味します。1度解いただけでこのレベルに達することは難しいため、3~4回は反復練習をする必要があるはずです。復習の際には計算ミスに気をつけて、「的確に計算するスピード」も身につけましょう。
問題演習で意識すること
数学の基礎力を身につけたら、センター試験の問題を解きます。「マーク模試」「センターの過去問」「センター試験の予想問題集」で演習を重ねましょう。
数学にそれほど苦手意識がない場合は、9~11月はマーク模試を受けるのみでも構いません。12月に入ったら本格的に予想問題や過去問を解き、センターの問題傾向や時間配分に慣れましょう。
ここからは、問題演習をするときに気をつけるべきことを紹介します。
大問1問につき15分。解ける問題から解く
センター数学は1A、2Bともに「大問4問」で構成されています。つまり1つの大問にかけることができる時間は15分です。ただ、見直しの時間を確保するためには、10分少しで解く必要があります。
いくら基礎や標準レベルの問題とはいえ、センター数学の問題は練られています。ときにはじっくり考える必要のある問題があり、こうした問題で戸惑っていると時間が足りなくなります。
問題演習をするときには、最初に大問全てをざっとチェックしましょう。そして「これなら解けそうだ」と安心できたタイミングで解き始めてください。また、途中で解き進められなくなったら次の大問へ移り、また解き進めましょう。
こうしてそれぞれの大問を行き来しながら問題を解けば、点数を伸ばしやすくなります。
「あとで解く問題」のマークに気をつける
上のように解けない問題を飛ばしていると、「マークミス」をしてしまうことがあります。本当は空けておくべきマーク欄に、次の回答を記入してしまうことがあるのです。
これはマーク式に慣れていても、うっかり行いやすいミスです。「マークは塗りつぶすだけだから簡単」と考えず、慎重に塗りつぶすように注意しましょう。
特にセンター試験本番は緊張しているため、普段はしないミスをしてしまうことがあります。日頃から「確実にマークする習慣」をつけておくことが大切です。
図形に関する問題は、必ず大きく図を描く
数1Aの「図形問題」や数2Bで出題される「ベクトルの問題」を解くときは、必ず図を描きましょう。計算だけで解き進めようとすると、途中で行き詰まることが多いです。図を書くことで余弦定理の利用を思いついたり、「一見すると気付きにくい角度の大きさ」などを見抜いたりすることができます。
また、辺の長さや角度の大きさは、イメージがつくように正確さを意識して描くと良いです。たとえば問題に「辺の長さが3、7、12の三角形」と書かれていたら、なるべくこの長さに近くなるよう図を描きます。30°や45°などの角度についても、できるだけ正しい大きさをイメージしながら描くと良いです。アバウトすぎる図を描くと、問題を解く手がかりとなるヒントをつかみにくいです。
前の問題がヒントになることがよくある
ひとつの大問は、複数の小問から構成されています。大問の後半になると、前半に出した小問の答えがヒントになることがよくあります。「小問で答えた辺の長さを使えば、面積を計算できる」のような流れです。そのため「前に出した答を使うことができないか」をいつも考えましょう。
数1Aの選択問題は「確率」と「整数」がおすすめ
数1Aでは大問4問のうち後半2問は、「選択問題」となっています。「場合の数と確率」「整数の性質」「図形の性質」の3問から2問を選択します。
おすすめは「場合の数と確率」と「整数の性質」の2問です。
確率は多くの受験生が苦手としやすい分野です。ただ、センターでは難しい問題が出題されず、基本~標準の問題が中心です。
確率で難しいのは「場合の数を、どのように数え上げるか」ですが、センター数学では比較的数えやすいパターンが多いです。また、整数の性質は式の変形・計算で解ける問題が多く、発想やひらめきをあまり必要としません。
これに対して「図形の性質」は、図を描いたりイメージしたりして、隠れた辺の長さや角度の大きさに気付く必要があります。これは決して難問ではないものの、ある程度「慣れ」が必要です。途中で解き進められなくなる可能性が高いため、図形の性質を選択することはあまりおすすめしません。
選択問題を確認したときに取り組みやすそうであれば、図形の性質を選択しても良いでしょう。基本的には確率と整数を選ぶほうが、得点率は高まりやすいです。
ただ、これはあくまでも目安です。試験開始の数分を使って問題を確認して、選択する問題を決めてください。
数2Bの選択問題は「確率・統計」も良い
数2Bの場合も、後半2つの大問は選択問題となっています。「数列」「ベクトル」「確率分布と統計的な推測」の3問から、2問を選択します。
数2Bに関しては、数列とベクトルに比べて、「確率分布と統計的な推測」は易しい傾向にあります。
確率・統計の分野は国公立の二次試験でほとんど出題されないため、多くの人があまり勉強しません。ただ、センター用に勉強すると、あまり労力をかけずに高得点を取りやすいです。
理系で数学の勉強をしっかりしているなら、センターの数列・ベクトルには十分対応することができます。一方、数学が苦手な場合や文系の場合は、確率・統計を狙ってみるのもおすすめです。まずは少し時間をとって、確率・統計の分野を学んでみると良いでしょう。そこで「できそう」と感じたら、そのまま勉強を進めましょう。もし難しいと感じたら、数列・ベクトルの勉強に専念すると良いです。
正確さとスピードを意識して問題演習を
ここでは「センター数学の対策方法」について紹介しました。
センター試験の数学は標準レベルであるものの、問題量が多いです。そのため基礎をしっかりと固め、「速く的確に解ける力」を身につけることが大切です。8月までには基礎を終えて、9月以降は問題演習を繰り返しましょう。また、センター本番では、マークミスなどのケアレスミスをしないよう注意してください。しっかりと対策すれば、センターの数学で高得点を取れるはずです。