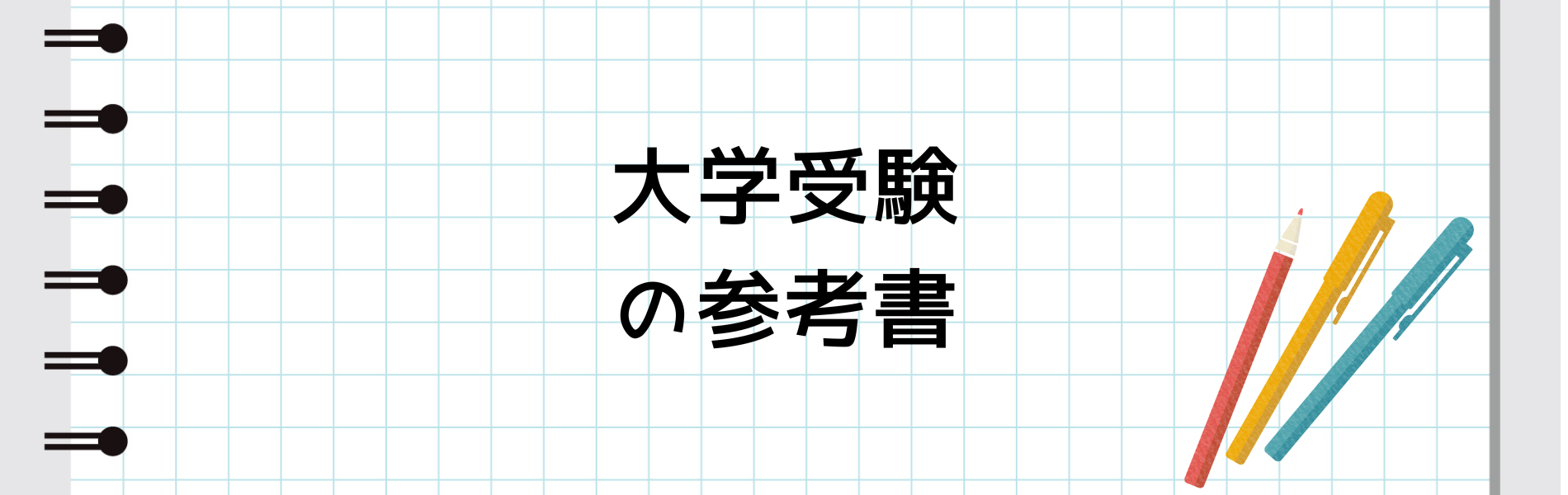※このページはプロモーション(広告)を含みます。

受験勉強を始めると、必ず受けることになるのが「模試(模擬試験)」です。模試では今の実力を測ることができ、「今後どのように勉強を進めるか」の指針になります。また、模試は「良問」が多いため、復習することで大きく実力をアップさせることができます。
ただ、メリットがたくさんあるにもかかわらず、模試を「受けただけ」で終わらせてしまうことは多いです。こうしたことにならないためには、正しい模試の活用法を知っておくことが大切です。
ここでは、模試の活用法を【受ける】【復習】【結果の分析】という3つの段階に分けて解説します。読むことで、模試を志望校合格のために最大限活用できるようになるはずです。
【受ける】1ヶ月半~2ヶ月に1回を目安に、積極的に受ける
普段の勉強は「知識のインプット」といえます。これに対して模試や受験本番は「知識のアウトプット」です。つまり「日ごろの勉強で学んだことを、実践で使えるかどうかを試す」のが模試です。
何ごとも、学んだだけでは上手く行うことができません。たとえば野球のルールをひと通り学んでも、すぐに野球を上手くできるわけではありません。野球が上手くなるには日ごろの練習と、試合で実践を積むことが大切です。
勉強もこれと同じで、日ごろから勉強することでのインプットはとても大切です。しかしこれだけでは不十分で、模試で実践を積むことで、学んだことを「使える知識」にする必要があるのです。
人によっては「結果が悪いと怖いから、模試を受けない」「今はまだ勉強が足りないから、模試を受けない」といって模試を避けることがあります。これは全く逆です。模試を受けるからこそ勉強をするようになり、実力がつくようになるのです。
そのため模試を定期的に受けて、受験勉強のペースメーカーにすることをおすすめします。
模試を受けるメリットは次の4つがあります。
- 本番の雰囲気に慣れることができる
- 問題形式に慣れることができる
- アウトプットすることで、知識が定着する
- 模試を区切りにして、勉強にメリハリをつけられる
これらについて、説明していきます。
本番の雰囲気に慣れることができる
受験生の多くは、模試を受けるときに緊張しています。誰もが「高い点数を取りたい」「目標とする偏差値に届かせたい」と思っているため、模試の会場には緊張感がただよっています。これは入試本番の会場で感じる雰囲気とよく似ています。そのため模試で慣れておくと、入試本番に慌てることなく対応できるようになります。
もちろん入試の会場では、さらに緊張感がただよっているかもしれません。しかし「模試のときよりも緊張するな」というように、模試である程度「心の準備」をしておくことができます。
私が塾で教えていたころ、模試に向けて頑張っていた女子生徒が当日に体調を崩し、試験の途中で退席してしまいました。その生徒は悔しそうにしていましたが、模試は入試本番ではありません。この女子生徒は、試験の緊張感を経験しておくことができただけでも良かったといえます。この生徒は入試本番は体調を崩すことなく試験を受けることができました。模試で慣れておいたおかげといえます。
問題形式に慣れることができる
大学受験の模試は大きく分けて3つあります。「マーク模試(センター試験の模試)」「実践模試(大学の二次試験の模試)」「大学別模試(難関大学の傾向に特化した模試)」です。
大学入試は受験生が共通で受ける「センター試験(以前の共通一次)」と、大学ごとに独自の問題を出題する「二次試験」があります。この2つは傾向が大きく異なり、センターはマークシートで番号を塗りつぶす「マーク式」、二次試験は解答用紙に途中式や答を書き込む「記述式」です。
そして二次試験の中でも、東大・京大・早稲田・慶応などの難関国公立大学・私立大学は、より特徴的な問題を出題します。
このように各試験の傾向に合わせて、模試も種類が分かれています。
それぞれの模試を受けることで、問題形式に慣れることができます。受験を有利に進める上で、問題形式に慣れておくことはとても大切です。問題を解くときに「いつものパターンだ」と思うことで、慌てずに問題を解くことができます。
アウトプットすることで、知識が定着する
友達に分からない問題を聞かれたときに教えると、自分の理解もより深まることがよくあります。これはインプットしていた知識を教えてアウトプットすることで、知識が自分のものになるためです。
模試を受けることはこれと同じで、今まで得た知識の「アウトプット」です。模試本番で問題を解けるように知識を思い返すことで、勉強した知識を「使える知識」に変換することができます。これを「知識が定着した」といいます。
いわゆる「頭の良い人」や「成績を伸ばす人」は、この作業をひんぱんに繰り返しています。つまり積極的に模試を受けることで、「インプット→アウトプット」のサイクルをたくさん繰り返すことができ、成績が伸びやすくなるのです。
模試を区切りにして、勉強にメリハリをつけることができる
受験勉強は高2の9~12月ごろから始める人が多いです。また、高3の4月から勉強を始めたとしても、受験期間は1年~1年半ほどあることになります。
こうした長い受験期間を勉強し続けていくには、メリハリをつけることが大切です。模試はメリハリためにとても良い機会です。
模試は上でもお伝えしたように「本番」です。「本番に向けて頑張ろう」と思うことで、より集中して勉強できるようになります。また、模試に向けて計画を立てながら勉強を進められるようになります。
逆に模試を受けないと、こうしたメリハリをつけることができないため、漠然と勉強を進めることになってしまいます。自分で計画を立てられる人なら良いですが、あまり自分できちんと進めることができる人は多くありません。模試を利用することで、強制的にメリハリをつけることができるのです。
河合・駿台・東進の模試を受けるようにする
大学受験の模試は大手3大予備校である「河合塾」「駿台」「東進」で定期的に開催されています。以前は代ゼミ(代々木ゼミナール)も大手予備校とされていましたが、最近は人気が低下しています。
また、学校によっては「進研模試(ベネッセ)」を高2、高3生に受けさせるところがあります。進研模試は上の3社に比べて問題がやさしく、河合や駿台、東進よりも偏差値が高めに出ます。しかし低めに出るほうを信頼したほうが高い実力をつけることができるため、進研模試はあまり重視しなくて良いです。
【復習】模試は良問の宝庫、必ず復習する
模試を受けたら、必ず復習することが大切です。模試はそれぞれの予備校が、受験生の実力を測定するために問題を考えています。その内容はとても考えられており、模試の問題は質・構成ともに非常に良い「良問」となっています。
単に模試を受けて結果を見るだけではもったいないです。模試を復習することで、実力アップに役立てることができます。
復習をしていなかった場合は、まずは受けた後に復習をする習慣をつけると良いです。そして復習する中で「復習の仕方」にもこだわると、さらに力をつけやすくなります。
復習の仕方はさまざまな方法がありますが、正直なところ正解はありません。工夫することで、自分に合った復習方法を見つけ出すことが必要です。ただ、効果的な復習方法は大きく分けて「模試の問題冊子を利用する方法」と「ノートを利用する方法」の2パターンに分かれます。この2つについて紹介します。
また、2つの復習方法に共通することとして、色ペンや好きなデザインのノートなどを活用すると良いです。楽しさを取り入れながら復習すると、取り組みやすくなります。
模試の問題に書き込む方法
模試は「問題冊子」と「解答・解説の冊子」に分かれています。このうち、問題冊子を「問題集」として活用します。解答・解説の冊子は細かな説明がたくさん書いてあるため、細かすぎます。そのため問題冊子を使います。
問題冊子の問題ごとに必要な途中式や答を記入して、「解答付き問題集」として仕上げます。書き込むときに、初回の復習も兼ねると良いです。そして問題集として仕上げたら、定期的に見直したり解き直したりして、知識を定着させます。
この方法は問題冊子をそのまま使うことができるので、手軽にできる方法です。ただ、模試本番のときにたくさん書き込みをしていると、あとで書き込みにくいことがあるのがデメリットです。
模試ノートを作る
模試ノートを作るのもおすすめの方法です。問題冊子をコピーして、コピーした問題を大問1問ごとに切り分けます。そしてノートの1ページに、大問1~2つを貼ります。問題の下に解答を復習を兼ねて書けば出来上がりです。あとは定期的にノートの見直し・解き直しをします。
この方法だと、自分のオリジナル参考書・問題集を作ることができます。また、ひとつのノートに模試の問題がまとまるため、復習しやすいのがメリットです。ただ、「ノートを作っただけで勉強した気分になりやすい」のがデメリットです。
きれいにノートを作るだけでは、成績は伸びません。当たり前のことではありますが、多くの受験生がしてしまいがちなことです。正直なところ、私も学生時代に経験があります。作業的なことはさっと終わらせて、知識のインプットとアウトプットに時間をかけることが一番大切です。
【結果の分析】一喜一憂せず、今後の勉強に役立てる
模試を受けてしばらくすると、結果が返ってきます。模試の結果で確認することが多いのが、志望校の合否判定・偏差値・各科目の点数です。これらを見て、喜んだり、落ち込んだりすることがあると思います。
これは誰しもあることですが、模試を成績アップ・志望校合格に役立てるためには、一喜一憂するだけで終わらないようにすることが大切です。合否判定や偏差値・点数の分析方法を説明します。
合格判定・偏差値は「ゴールまでの距離」
合否判定と偏差値は、「ゴール(志望校)までの距離」と考えてください。合否判定が良い・偏差値が高いほど、合格に近付いているといえます。
合否判定がA~Bの場合、入試本番でも合格の可能性がかなり高いです。素直に喜んで良いですが、油断しないように気を付けましょう。受験生は全員が必死に勉強しています。追い抜かされてしまう可能性があるため、引き続きしっかりと勉強していきましょう。
合否判定がC以下の場合は、現時点では合否の可能性が低いです。もちろん落ち込んでしまうと思いますが、気持ちを切り替えることが大切です。「あとどれだけ時間が残っていて、これから何をするべきなのか」を考えましょう。
夏前などでまだ余裕があるなら、これからの勉強次第で十分に挽回できます。秋や冬で合否判定が低い場合は、すべり止めの大学を考えたり、第一志望の大学を変更したりする必要があります。大学を変えることになっても、他で魅力的な大学を見つけるきっかけになることもあります。悔しい気持ちがあるかもしれませんが、気持ちを落としすぎないようにしましょう。
科目ごとの点数で、得意・苦手科目が分かる
各科目の点数を見ることで、得意科目と苦手科目を知ることができます。ここで、「得意科目を伸ばすことに力を入れる」「苦手科目を克服する」など、今後の勉強をどのように進めるかを考えることができます。
苦手科目が平均点を下回っているなら、苦手科目を重点的に勉強することをおすすめします。受験勉強を進めると、それぞれの科目に共通する「理解力」を鍛えることができます。そのため苦手科目でも今の力でもう一度考えてみると、理解できることがよくあります。
80点を90点に伸ばすのは大変ですが、40点を60点に伸ばすのは意外とできることが多いです。このように苦手科目を模試で把握して、「底上げ」をはかりましょう。
また、得意科目が分かり、まだ伸ばせる余地があると思ったら、得意科目をさらに勉強するのも良いでしょう。
単元ごとの点数で、得意・苦手な単元が分かる
各科目の点数を確認したあとは、科目の単元ごとの点数も確認すると良いです。数学の中でも『「関数」は点数が良いけれど、「確率」は点数が悪い』のように、単元ごとに点数のばらつきがあるはずです。このようにより細かく点数が低い単元を見つけることで、効率良く点数アップにつなげることができます。
模試は受験勉強の重要ツール。しっかり活用を
ここでは大学受験のために模試を活用する方法について紹介してきました。「模試の受け方」「復習の仕方」「分析の仕方」に気をつけることで、模試を最大限に活用できるようになります。
この記事を読んでも、模試を使いこなすには慣れが必要です。最初は模試を上手く活用できないかもしれません。ただ、活用法を読み返して勉強に取り入れるように気をつけていれば、とても良い勉強ツールになってくれるはずです。ぜひ模試を活用して、受験勉強をより良いものにしてほしいと思います。