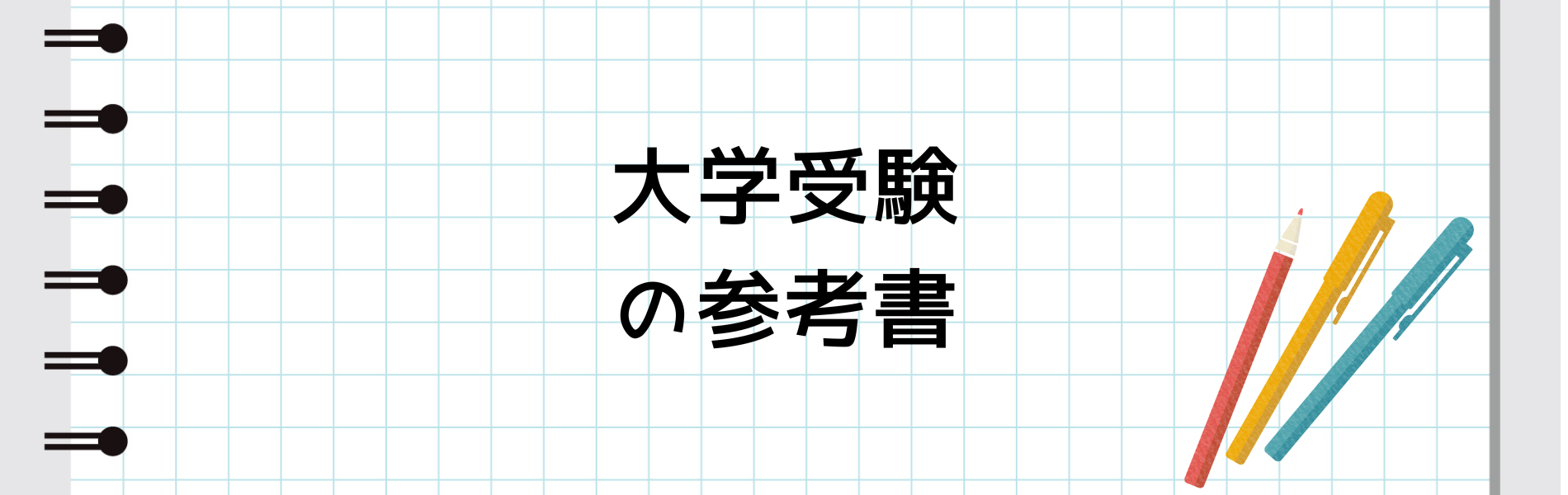※このページはプロモーション(広告)を含みます。
立命館大学志望のお子さんをサポートするために、親御さんとしてできる準備のひとつが「入試方式や日程の把握」。
立命館は方式の種類が多く、出願パターンや受験日も複雑になりがち。
お子さんに勉強を頑張ってもらうために親が確認しても、「なにこれ」「よくわからない…」となることも多いものです。
そこでこの記事では、立命館の入試方式の全体像を整理して、それぞれの特徴・違いを解説。
それぞれの入試方式がどんなものなのかを知ることで、より良い出願戦略に役立ち、受験に向けた準備もスムーズになるため、ぜひ参考にしてくださいね。

私は大学受験の講師として10年以上教える中で、立命館を受ける生徒さんも数多く見てきました。
ただ、勉強に集中していて受験方式を把握していなかったり、冬になって出願で慌てるケースもあったりしたため、早めに確認しておくことは大切。
ここは親御さんもサポートしやすい部分のため、ぜひ参考にしてくださいね。
(入試情報はこちらを元にしています)立命館大学:一般選抜入試方式
立命館の入試方式、まずは全体像をチェック!
立命館大学の入試は方式やスケジュールが複雑で、親御さんも「分かりにくい」と感じることが多いです。
特に立命館以外の大学も受験する場合、方式の違いや日程の把握はとても重要。
まずは立命入試の全体像を確認しましょう。
立命館の入試方式は大きく4種類
立命館は受験生がベストを尽くせるよう、大きく4種類の入試方式を用意しています。
- 立命館の独自試験のみで合否が決まる
- 立命館の独自試験 + 共通テストで合否が決まる
- 共通テストのみで合否が決まる
- 一部、特殊な入試方式
複雑ではありますが、幅広い形式で受験できるというのは、受験生に配慮した結果でもありますね。
入試方式1:立命館の独自試験のみで合否が決まる
合格定員数が多く、立命館の中で1番スタンダードな入試方式。
立命館が独自に作成した問題で、大学が直接採点・合否判定を行います。
入試方式2:立命館の独自試験 + 共通テストで合否が決まる
立命館の入試前に実施される「共通テスト」と「立命館の独自問題」の点数を合計して、合否を判定する方式。
共通テストの問題は基礎〜標準レベルで、立命館の問題より少しやさしめ。
共通テストで点をしっかり取れれば、合格に近づきやすくなります。
ただ、共通テストは独特の傾向があり、これに合わせた対策が追加で必要。
勉強することが増えるため、基本的には独自試験のみのほうが一般的です。
入試方式3:共通テストのみで合否が決まる
立命館が実施する独自試験は受けず、共通テストの得点だけで合否が決まる方式。
共通テストで高得点(7〜8割)が取れれば、それだけで合格に。
ただ、共通テストで7〜8割を取るのは、これはこれで大変ではあります。
入試方式4:一部、特殊な入試方式
立命館には一部、特殊な入試方式も2種類あります。
当てはまる場合は検討してみるのも良いでしょう。
・国際関係学部のIR方式
国際関係学部を志望する人のみが対象の方式で、立命館の独自試験に加え、英検・TOEFL・IELTS・GTEC・TEAPのスコアも加味される入試方式。
英語力に自信のある受験生にとっては有利になります。
・経営学部経営学科の「経営学部で学ぶ感性+共通テスト」方式
共通テスト65%の得点に加え、立命館独自の試験(記述式)の点数の合計で合否が決まる方式です。
対策がしにくいため、独自試験のみの方式でも良い気はします。
メインは2月実施の「前期試験」。3月実施の「後期試験」も一応ある
立命館の入試は
- 2月に実施の「前期試験」
- 3月に実施の「後期試験」
に分かれていて、これはほかの私立大学でも一般的なスケジュール。
上で挙げた4方式の入試が、前期・後期それぞれで実施されます(片方にしかない方式もあり)。
立命館の入試は大部分が2月上旬に集中していて、前期試験が最大の山場。
後期試験は共通テスト利用型が中心で、チャレンジや滑り止めに使われるため、前期で合格を決めるのが基本の受験戦略です。
同じ入試方式でも複数の日程があり、複数回受験できる
立命館は同じ入試方式でも受験日が複数組まれていて、併願(複数回受験)ができます。
問題は日によって変わり、回数を増やすことで合格のチャンスを増やせます。
2月の前期試験で受けられる入試方式
ここからは立命入試の中でも受験者が多く、合格枠も多い2月の前期試験に受けられる入試方式を見ていきます。
立命館の独自試験のみの入試方式
全学統一方式
最もメインの入試方式で、文系の全学部、理系の全学部で同じ問題を使う入試方式。
ひとつの試験で複数学部に出願できるのが魅力です。
同じ試験日でも、指定の専攻・学科なら、2つまで希望を出せます。
学部個別配点方式
全学統一方式と出題形式は同じで、各学部が定めた配点で試験が行われる方式。
得意科目を活かしやすく、学部ごとの特徴が色濃く出ます。
全額統一方式に続いて人気です。
理系型3教科方式
文系でも数学が得意な人向けの方式。
数学を重視しつつ、3教科でバランスよく受験する方式です。
利用できる学部が決まっています。
薬学方式
薬学部独自の方式で、理科や数学に重点を置いた出題内容。
薬学部志望の場合は考えてみると良いでしょう。
立命館の独自試験+共通テストの入試方式
共通テスト併用方式
立命館が実施する独自試験に加えて、共通テストの得点も合わせて合否が決まります。
科目数が増えるため準備は大変ですが、競争率が低くなるのがメリット。
また、共通テストの形式が得意、国公立大学も受験する場合などにも向きやすいです。
共通テストのみで合否が決まる方式
共通テスト方式
共通テストの成績だけで合否を判定する方式。
立命館の独自試験を受けに行く必要なく、共通テストを受けたあとに出願するだけで終了。
立命館が第一志望でないなら、サブとして出すのも良いでしょう。
特殊な入試方式
国際関係学部のIR方式
TOEFLやIELTSなどのスコアを利用。
英語が得意な人におすすめです。
3月の後期試験で受けられる入試方式
3月にある後期試験は定員が少なくなり、競争率もやや高め。
基本的には前期試験で合格を決めるか、後期は受験しない人が多いものの、他大学を受験する人や「立命合格のラストチャンス」として利用されることもあります。
前期試験のあとでも出願できるため、合格を勝ち取れなかったときの再チャレンジとして視野に入れておくのも良いでしょう。
後期分割方式
「立命館の独自試験+共通テスト」または「立命館の独自試験のみ」のどちらかで合否が決まる方式。
学部によってどちらかは決まっています。
経営学部経営学科の「経営学部で学ぶ感性+共通テスト」方式
上でも触れましたが、「共通テストで立命館が指定する3科目で65%以上の点数」+「記述式で回答する立命館の独自試験」の合計で合否が決まる方式。
記述問題は経営に関する問題が出題されるため、日頃から関心をもっている人に向いています。
ただ、3月に実施されるため、この方式に集中して対策するのはおすすめできません。
共通テスト方式
共通テストの点数のみで合否が決まる方式。
前期試験にもありますが、後期試験にもあります。
2月に出願しなかった人でも、後期の期日までに出願すれば合格のチャンス。
ただ、共通テストで8割ほどは得点する必要があり、これくらい取れる学力があれば前期で合格できることがほとんどではあります。
立命館のおすすめ入試方式は?
ここまで、立命館の入試方式をひと通り解説してきました。
たくさん方式があり、どの方式で受けるべきか迷う受験生も多いです。
ただ、立命館の優先度が高い場合、まず受けるべきなのは、前期の「全学統一方式」と「学部個別配点方式」。
この2つは合格定員数が多く、複数日程を受験すれば合格できる可能性が高くなるためです。
これに加えて共通テスト併用方式も良いかもしれませんが、共通テスト対策の時間・負担が増えるため、それほどおすすめではありません。
共通テスト利用・後期試験は、より上位の大学を受ける人向け
共通テスト利用・後期試験は、「立命館が本命ではないけれど、受かればラッキー」という位置づけで使われることが多い入試方式。
第一志望が立命より上位の大学を考えているならおすすめです。
立命館の入試方式は複雑。違いを知り、しっかり確認を!
立命館は学生数がとても多く、入試方式もその分だけ複雑。
「入試方式を調べて子どものサポートをしたいけど、よくわからない…」となることもあると思います。
ただ、しっかり確認おけば「全学統一方式を受ければいいから、この日程で入試があるんだな」と親御さんも把握しやすくなり、お子さんの受験期間を助けてあげられます。
ぜひここまでを参考に、受験する方式選びや受験スケジュールの計画を練ってくださいね。
ちなみに、「まだ受験方式に迷っている」「成績が伸び悩んでいて焦っている」などの悩みがあるなら、ラストスパートとして家庭教師で直前対策をするのもひとつの方法。

家庭教師のトライなら大学受験に強い先生が数多く在籍、1対1指導のため立命の過去問演習やお子さんの弱い部分をピンポイントで集中対策してもらえます。
また、スタッフも立命館の入試に詳しいため、出願する入試方式や他大学の受験スケジュールの調整などもアドバイス。
お子さんへ提案する前に、「今の状況で、うちの子は家庭教師をやるべきか、必要かどうか」を相談することもできるため、まずは親御さんだけで話を聞いてみるのもおすすめです。![]()